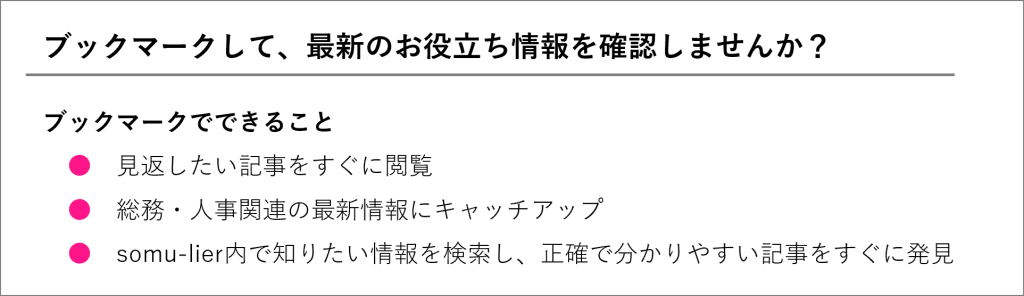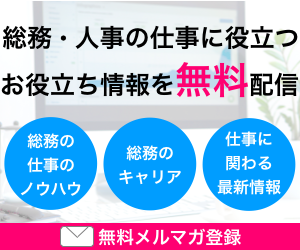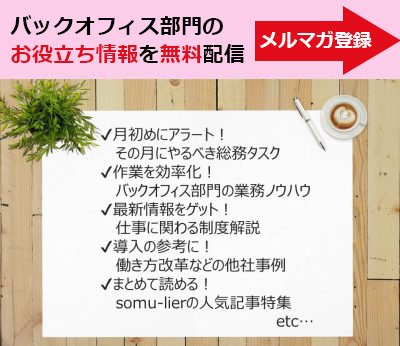労働基準法では、労働時間は基本的に1日につき8時間、1週間で40時間までと定められています。また、使用者は原則として週1日以上の休暇を与える必要があり、1週間以上の連続勤務をするためには変形休日制を導入しなくてはなりせん。今回は、変形休日制を導入した場合としていない場合の連続勤務日数の上限、連続勤務時間と勤務間インターバル制度の関係、連続勤務の危険性について解説していきます。
目次
連続勤務日数の上限
労働基準法上における雇用形態ごとの取り扱いについて
日本において、労働条件に関する種々の基準を定めているのは労働基準法です。雇用形態には正社員だけでなく、契約社員、パート、アルバイトなど様々な形態が存在しますが、労働基準法は原則として雇用形態による条件の差を設定していません。そのため、以下で解説していく連続勤務日数の上限や連続勤務時間などに関しては、すべての雇用形態において共通であり、どれも労働者一般の規則として定められていると考えてください。
連続勤務日数
労働者の休日は、労働基準法第35条第1項および第2項において、以下のように定められています。
- 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない
- 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者について適用しない
基本的には第1項が適用されることになり、就業規則で定められていない場合は1週間の起算日は日曜日になります。したがって、日曜日を休日として、月曜日から翌週の金曜日まで出勤日、翌週の土曜日を休日にするというような勤務も可能ですので、第1項を適用した場合には最大で12日の連続した勤務が可能ということになります。
変形休日制を導入した場合の連続勤務日数
一方で、第2項では特定の4週間において4日間の休日が与えられていれば良いとされ、このような形態を変形休日制と呼びます。第2項を適用して変形週休制を導入する場合には、上記の12日という連続勤務の上限規定が当てはまりません。例えば、月の最初の3週間(21日)はずっと勤務し、4週目のうち最後の4日間だけを休日にするという勤務体系で、最大24日間連続して勤務することも法的には可能になります。ただし、この第2項のような休日規定を導入する際には、就業規則に明記することが必要となり、また、変形休日制の単位となる4週間の起算日を定めなくてはなりません。
関連記事:
・知らないと恥ずかしい?人事担当者なら知っておきたい労働基準法
・【2024年5月更新】残業代はすべて割り増しに?労働基準法で定める割増賃金とはどんなもの?
・有給休暇が「5年間」有効に?労働基準法消滅時効に改正の動き
連続勤務時間と勤務間インターバルの関係
連続勤務時間
労働時間に関しては、労働基準法第32条で1日8時間、1週間で40時間と上限が規定されています。しかし、一定の条件を満たした場合には、1ヶ月単位の変形労働制や1年単位の変形労働制を導入することも可能です。1ヶ月単位の変形労働制とは1ヶ月の労働時間を平均して1週あたり40時間にする制度であり、1年単位の変形労働制では1年の労働時間を平均して1週40時間にします。
一方で、1週間あたり平均40時間の労働時間を超えて行う労働を法定時間外労働と呼び、これがいわゆる残業に当たります。このように所定の時間を超えて時間外労働を行う場合や休日労働を行う場合には、1日、1日以上3ヶ月以内、1年間のそれぞれの単位で、あらかじめ時間外労働・休日労働規定(いわゆる「36協定」)を締結し、労働基準監督署長に届けなければなりません。
36協定を締結した場合の時間外労働の限度は、一般の労働者の場合について以下のように定められています。カッコ内は対象期間が3ヶ月を超える1年単位の変形労働時間制の対象者の場合を示しています。
- 1週間:15時間(14時間)
- 2週間:27時間(25時間)
- 4週間:43時間(40時間)
- 1ヶ月:45時間(42時間)
- 2ヶ月:81時間(75時間)
- 3ヶ月:120時間(110時間)
- 1年間:360時間(320時間)
勤務間インターバル制度について
連続勤務時間を考える上では、勤務間インターバル制度を踏まえておくことも必要です。勤務間インターバル制度とは、勤務の終業時刻と翌日の始業時刻との間を一定時間あけ、労働者の休息時間を確保することで、実質的に労働時間を短縮するという制度です。2018年6月29日に成立した「働き方改革関連法」に基づき、2019年4月1日より、勤務間インターバル制度は事業主の努力義務として規定されています。
連続勤務時間と勤務間インターバル制度の関係について、具体例として11時間のインターバルを設定したケースを考えてみましょう。始業時刻が午前9時、終業時刻が午後6時の企業にて、仮に午後11時まで労働を行なったとします。そうした場合、勤務を終えた時刻である午後11時からインターバルの11時間が経過した午前10時が、翌日の始業時刻となります。本来の始業時刻である午前9時との差1時間分については、時差出勤を行うことで対応したり、勤務したとみなして通常通りの賃金を保証したりするなどして対応することが一般的です。
勤務間インターバル制度ではEUの導入事例が有名となっていますが、国内でも2017年ごろから勤務間インターバル制度を導入する企業が増加しており、今後も導入企業は増えていくと考えられています。
連続勤務の危険性
連続勤務が長期間にわたって頻繁に生じると、心身両面での危険性が高まります。身体的な面では、連続勤務によって身体のだるさが続く、集中力が低下する、腹痛や発熱、風邪をひきやすくなるなどの身体の不調が生じやすくなります。他方、精神的な面では、勤務終了後や休日にも仕事から気持ちを切り替えることができず、常に仕事のことが頭にあり十分に休めなかったり、休日にも趣味などをする気が起きなくなってしまったりなど、プライベートにも影響が出てしまうようになります。
このように労働者が身体面、精神面ともに疲弊している状況では、労働者の健康状態が危惧されることはもちろん、仕事のパフォーマンスが下がり生産性が低下するなど、企業にとってもデメリットが多く存在します。法に抵触していないからといって過度な連続勤務を労働者に強いることがないよう、社内の制度の整備や雰囲気づくりを心がけていくことが求められます。
関連記事:
・STOP労働災害! 日常でできる労災の防止策を紹介
・【2019年4月~】管理職の労働時間の把握が義務化されます!
まとめ
今回は、変形休日制を導入した場合としていない場合の連続勤務日数の上限、連続勤務時間と勤務間インターバル制度の関係、連続勤務の危険性などについて解説してきました。この機会に、社内の労働環境についてあらためて見直してみてはいかがでしょうか。